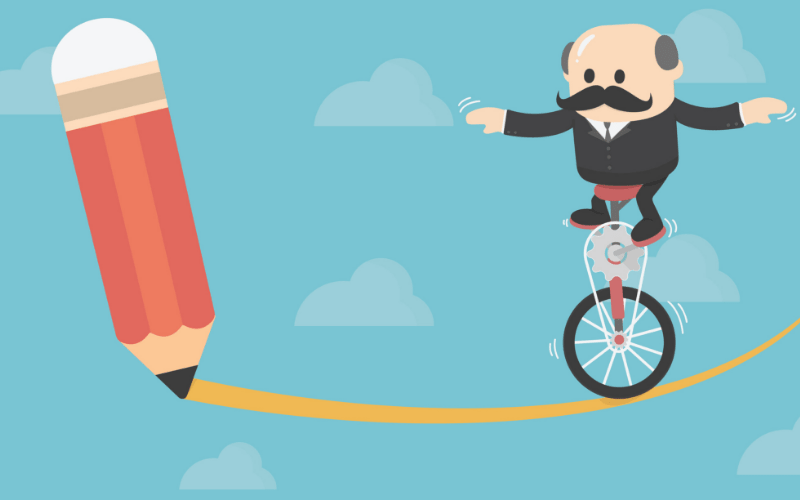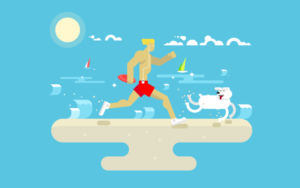「出向制度」は以前から存在しましたが、ここ最近、人材育成や雇用調整に役立つと再注目されています。
出向元、出向先、従業員のそれぞれの立場から見る「出向制度」のメリット・デメリットは何があるのでしょうか。
今回は「出向制度」の目的、気になる給与の扱いについて詳しく見ていきましょう。
出向とは

「出向」とは、出向元企業との雇用契約は変わらず別の企業へ異動することをいいます。
例えば、親会社から子会社への出向の場合、現場での仕事は子会社側の指示に従って行いますが、給与は親会社から支払われる形です。
企業間で行われる大規模な出向となれば、職場の雰囲気や人間関係も大きく変わり、仕事内容も異なります。
企業グループの発展、人事戦略のために、親会社から実績あるリーダーを出向するケースがあります。
出向と派遣の違い
「出向」と似た雇用形態は「派遣」がありますが、両者の違いは何でしょうか?
「派遣」の働き方は、派遣社員は派遣元と労働者派遣契約を結び、指揮命令権は派遣先となります。
「派遣」の場合は、使用者と雇用者が異なるため、派遣先は時間外労働や休日労働をさせることはできません。
社員が別企業で働くという意味では「出向」と「派遣」は同じです。
一般的な出向期間は半年から1年以上の長期契約となることが多く、それに対して派遣の契約期間は、
短期契約になる場合が多いです。

出向と左遷の違い
では、「出向」は「左遷」と何が違うのでしょうか?
「左遷」とは、一般的に今までの地位よりも降格する人事異動のことをいいます。
役職は変わらなくても本社から地方支社への異動や社内で業務が少ない部署への異動も「左遷」となります。
出向と転籍の違い
「出向」と「転籍」はどちらも出向先・転籍先の指揮命令の下で就労させる共通点があります。
ただし、「出向」は出向元との雇用契約が継続していますが、「転籍」は転籍元との雇用契約が終了している点が異なります。
出向の目的

出向を行う目的は、経営・技術指導、雇用機会の確保、職業能力開発、グループ企業内の人事異動などが挙げられます。
業績の向上や労働環境の改善
大企業の場合は、様々な関連会社の仕事に精通していることは重要なポイントです。
個人の業績を上げるためにも、インターンシップのような感覚で、勉強と経験の機会を与えるために出向させるケースは多くあります。
人材の育成
出向元企業では経験できない地位や職務を経験させるために、人材の育成、能力開発を支援する目的で
出向を行うケースがあります。
優秀な人材を子会社、関連会社に出向させて、出向先の技術や経営戦略を習得するのが目的です。
雇用調整
自社での雇用が難しい場合、自社での管理ポストが不足している場合に、雇用調整の目的で出向をすることがあります。
人材交流
グループ企業、取引の多い企業同士が人材交流のために出向させて、職場環境の活性化を図ります。
出向する場合の期間はどれくらいか
従業員を関連会社に出向させる場合の期間は制限があるのか気になるところです。
実際には、法律で定められている出向期間に関しての制限はなく、出向元と出向先の取り決めによって決定されます。
業務上の必要性がない場合や人選の合理性に欠ける場合は、権利の濫用により出向が無効になることがあるので注意しましょう。
出向のメリット・デメリット

ここからは、出向する社員、出向元、出向先の目線から出向を行うメリットとデメリットを見ていきましょう。
出向する社員のメリット・デメリット
20代から30代の若手社員の場合は適応力に期待できるため、技術やコミュニケーション能力を高めることができます。
他社で仕事をすることで、新たな人脈をつくり、自社を客観的に分析できるようになるのもメリット。
出向先会社で身に付けた業務のやり方を自社に戻った時に活かして、自信に繋げることができます。
若手社員の研修を目的として出向の場合は、職場環境が急に変わることによるストレスや戸惑いもあるため、メリットを感じるまでに時間がかかります。
職場環境に慣れないまま出向期間が長期化した場合は、自社への不信感も強まり、逆にモチベーションの低下となるのがデメリットです。
出向元のメリット・デメリット
出向元から見るメリットは、経験不足な若手社員を子会社や関連会社、取引先会社に出向させれば、人材育成に役立ちます。
優秀な社員を出向させれば、出向先の経営の立て直しを図ることができます。
大企業の場合は、人材育成目的で出向させるケースが多く見られますが、近年は人件費削減のために出向かせる会社も多いです。
ただし、出向社員に雇用調整を目的とする出向だと分かった場合、トラブルが発生する可能性があるので注意が必要です。
出向先のメリット・デメリット
優秀な出向社員を迎えた場合は、出向先の業務効率は上がり、職場全体の活性化に繋がります。
グループ企業の本社から子会社へ出向する場合は、本社との信頼関係を築くでことができるのもメリット。
グループ内の最新の情報を入手したり、グループ内でより円滑に業務を進めていくことが可能です。
デメリットとしては出向社員の受け入れ体制を整える必要があり、人件費が増えるのはデメリットと言えます。
そして、必ずしも受け入れ社員が即戦力になる訳ではなく、人によっては現場に合う・合わないがあります。
出向する際の給与などについて

出向の場合は、出向元、出向先のそれぞれに労働契約関係があり、両者間で交わされる出向契約にて取り決めが行われます。
給与の支払いについて
給与の支払いについては、出向元と出向先との協議によって決めることになります。
一般的には、出向元が社員に全額を払い、負担金を出向先から出向元に支払うケースが多いです。
出向先での支払いにすると、各種保険料の手続きが複雑化するので、出向元が支払うケースが多くなっています。
一般的には、身分に係わる事項(賃金、解雇、退職、定年)は出向元の就業規則を適用させます。
業務遂行に係る事項(労働時間、休日、休暇、服務規律)は出向先の就業規則を適用することが多いです。
社会保険や労働保険などについて
社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は出向元が出向社員の全ての賃金を支払う場合、雇用保険と同じ手続きになります。
出向元と出向先の両方が一定割合で賃金を支払う場合は雇用保険の扱いが変わります。
この場合、出向元での被保険者資格は継続され、出向先の方でも資格取得手続きが必要となります。
出向社員はどちらの被保険者になるのかを選択する必要があり、選ばれた出向元または出向先が「二以上事業所勤務届」を年金事務所に届出ます。
その後は、出向元、出向先のそれぞれで按分された保険料を納付していく形です。
労災保険については、出向社員が出向期間中、出向先だけで業務を行っている場合は、出向先の整理になります。
出向社員が出向先で被った業務災害、通勤災害の各種申請にかかる手続きは出向先が行わなければなりません。


まとめ

「出向制度」は、出向社員と出向元、出向先のそれぞれに労働契約関係があることになります。
就業規則の適用は、出向元と出向先との間で交わされる出向契約で決定されるので注意しましょう。
出向先の就業規則を適用させる際には、出向元の待遇よりも悪くなり、従業員とトラブルにならないように注意が必要です。