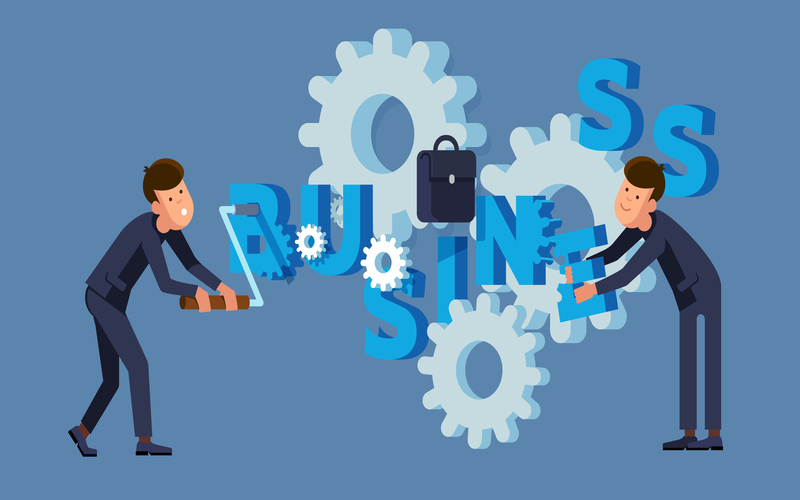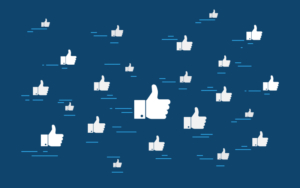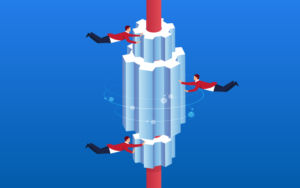企業がマーケティング活動をするとき、様々な分析やフレームワークを活用することになります。この記事では、有力な分析方法の1つであるKSF分析について、その概要からなぜ重要なのか、関連する分析方法について解説します。
KSF分析とは
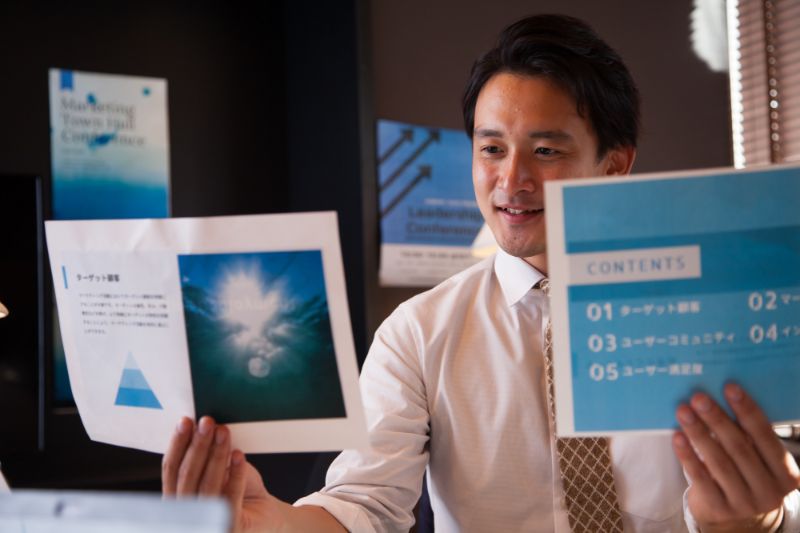
KSF分析のKSFとは、(Key Success Factor)の頭文字をとったものです。日本語にすると「鍵になる成功因子」となります。事業で成功を収めるときに重要になるポイントだとイメージしておきましょう。
このKSFは、企業が戦略や目標を立てる際の重要な要素となります。販売戦略やマーケティング戦略など様々な戦略を立てる際に活用されます。
KSFが重要な理由
KSFが重要とされる背景には、企業における戦略立案の重要性が高まっていることが挙げられます。近年では、市場に様々なサービスや商品が並んでおり、ユーザーのニーズに対応できるかどうかが重要になっています。
また、インターネットやSNSが普及したことで競合他社よりも優位なポジションを得るにはスピードも求められます。 つまり企業は、多様なニーズに対応しながらもスピードが求められるという難しい状況に直面しているということ。
戦略を立案した上で事業を推進することが必要となり、その際にKSFを活用するため、KSFの重要性が高まっているのです。
KSFの関連用語

KSFには、様々な関連用語があります。スペルが似ているので間違えないように注意してください。
KSFとKBFの違い
KBFは(Key Buying Factor)の頭文字をとったもので、「購買決定要因」と訳されます。これは、お客さんが商品やサービスを購入するかどうかを決めるときに重視する要素のことです。例えば、お菓子を買う場合ならカロリーや糖質、炭水化物、価格、デザイン、ブランドなどが要素として挙げられます。これらの中から、自社製品のターゲットとなる人のKBFを把握します。
KSFとKGIの違い
KGIは(Key Goal Indicator)の頭文字をとったもので、「重要目標達成指標」と訳されます。 これは、企業経営における最終目標の達成具合を評価する指標のことです。指標は売り上げや利益率、契約件数など数値によって設定されます。
KSFとKPIの違い
KPIは(key performance indicator)の頭文字をとったもので、「主要業績評価指標」と訳されます。経営や各種事業などの戦略目標達成に対して現時点でどのくらいの進捗具合なのかを把握するための指標です。
最終的な目標に対する中間地点での目標だと考えてください。 週単位や月単位など一定の期間で計測し、状況を把握することで状況の改善やさらなる向上を目指すことができます。
KSFを整理するためのフレームワーク

ここからは、KSFを抽出する際に活用できるフレームワークを紹介します。
3C分析
3C分析は以下の3つのCをベースに行う分析です。
- Customer(市場・顧客)
- Competitor(競合)
- Company(自社)
分析では、最初に市場・顧客の分析を行い市場の現状や顧客のニーズなどを把握します。次に競合分析を行い、競合の強みと弱み、動向などを把握します。そして最後に自社を分析し、自社の状況を把握し競合と比較しながら、競合との差別化を図れるKSFや優位性を得られるKSFを抽出していきます。
SWOT分析
SWOT分析は以下の4つの視点から行う分析です。
- Strengths(強み)
- Weaknesses(弱み)
- Opportunities(機会)
- Threats(脅威)
StrengthsとWeaknessesは自社の内部環境が、OpportunitiesとThreatsは、自社以外の外部環境分析が該当します。 分析では、最初に外部環境について分析し、自社にとって機会となる、もしくは脅威となる要因を把握します。次に自社の強みと弱みを分析します。それぞれの分析が終わったら以下のようなクロス表にして内部環境と外部環境を掛け合わせ優位性や差別化につながるKSFを抽出します。
| 強み | 弱み | |
|---|---|---|
| 機会 | ||
| 脅威 |
5F分析
5F分析は、以下の外部環境の要因をもとに行う分析です。
- 業界内競合
- 売り手
- 買い手
- 代替品
- 新規参入
業界内競合は、業界の成長性や競合のブランド力などを把握します。また、売り手では、売り手の力で原材料費が高騰し利益を低下させるものを、買い手では、買い手の力で商品価格が低下し利益を低下させるものがなんなのかを把握します。
さらに代替品では自社の製品に取って代わるものがなんなのかを分析し、新規参入では、新規参入に伴い自社製品の脅威になるものがなんなのかを分析します。
これらを分析することで、業界全体の構造を把握し、自社が優位になるためのKSFの抽出を図ります。
PEST分析
PEST分析は、以下の4つの要因から行う分析です。
- Politics(政治)
- Economy(経済)
- Society(社会)
- Technology(技術)
分析を行うことで各要因の現状について把握することができ、自社の狙い所や差別化を図れるポイントなどが見えてきます。
ちなみに、4つの要因の具体例としては以下のようなものが挙げられます。 ・政治:法改正、政治動向など ・経済:景気、株価、物価など ・社会:人口、流行など ・技術:新技術、特許など
その他マーケティング戦略に関するフレームワークや理論
ここまで紹介したもの以外にも、マーケティング戦略に活用できるフレームワークや理論には様々なものがあります。どのようなものがあるのか、解説していきます。
STP
STPは、Segmentation(市場細分化)、Targeting(狙う市場の決定)、Positioning(自社の立ち位置)の頭文字をとったもので、マーケティングにおいては、これをもとに分析を行います。
大まかなイメージでいうと、セグメンテーションで市場全体の現状を把握し、ターゲティングによって、市場の中でもどこを狙うのかを決め、ポジショニングによって自社の立ち位置を決め、競合他社との関係を決めるというものです。 新たにビジネスを始める時などに活用できるフレームワークです。
4P
4Pは、以下の4つの要素のことです。
- Product(製品)
- Price(価格)
- Place(流通)
- Promotion(販売促進)
4Pは、簡単にいうと、どんな製品を(Product)、どんな価格で(Price)、どのような流通経路で(Place)、どのような層に販売していくのか(Promotion)を決めるためのフレームワークです。

イノベーター理論/キャズム
イノベーター理論は、商品やサービスを購入する消費者の購入時期を分類したもので、以下の5つに分かれます。
- イノベーター(革新者)
- アーリーアダプター(初期採用者)
- アーリーマジョリティ(前期追随者)
- レイトマジョリティ(後期追随者)
- ラガード(遅滞者)
上から順番に早い段階で商品やサービスを購入している層となり、最後のラガードは最も保守的な層となります。また、市場で多いのはアーリーアダプターとアーリーマジョリティとなっています。
そして、キャズムとは、イノベーター理論におけるアーリーアダプターからアーリーマジョリティに商品やサービスが割る際に存在する障害のことです。


AIDMA
AIDMAとは、消費者の購買行動を示すモデルのことです。消費者は以下のステップで商品を購入すると考えられています。
- Attention:商品の存在を知る
- Interest:興味を持つ
- Desire:欲しいと思うようになる
- Memory:商品のことを記憶する
- Action:実際に購入する
購入までのプロセスを複数の段階に分解することで、消費者がどの段階にあるのかが見極められるようになり、消費者の段階に応じた戦略をとることが可能になります。
AISAS
AISASは、AIDMAの考え方をベースに、消費者のインターネットが普及した現代に合わせる形にしたものです。消費者は以下のステップで商品を購入すると考えられています。
- Attention:商品の存在を知る
- Interest:興味を持つ
- Search:インターネットで検索する
- Action:実際に購入する
- Shere:インターネットやSNSで共有する
AIDMAとの違いは、興味を持ったらインターネットで検索し、実際に購入した後に使った感想などをSNSや口コミサイトなどで共有する点です。この共有された情報は次の消費者が購入する際にも活用されるため、消費者の行動がどんどんリンクしていくことになります。
カスタマージャニー
カスタマージャーニーは、消費者が商品の購入に至るプロセスのことです。どのように商品と接点を持って、関心を持ち、実際に購買に至るのか、その道筋をジャーニー(旅)に例えています。消費者のプロセスを時系列にしていることで、タイミングに応じた情報提供が可能になります。

まとめ

今回はKSF分析の概要と、様々なフレームワークについて解説しました。フレームワークは企業が戦略を立案する際に欠かせないものです。様々な種類があり、用途も異なるため、利用する際は分析を行う目的と照らし合わせるようにしてください。